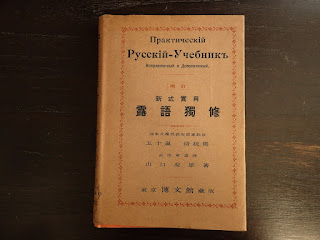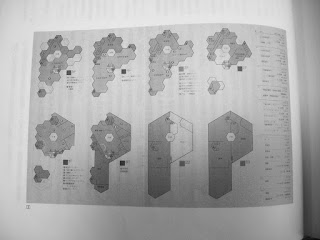この曾祖父の訳書『嗚呼 此の一戦』については以前に書いたことがあったが、この訳書と同年の明治45年に同じ博文館から刊行され、数年後に重版された『新式実用 露語独習』増訂版も古書店で見つけて購入した。数年前から国会図書館のデジタルコレクションで公開されていて、実用とするにはあまりも古めかしいことは知っていたが、開いてみたら以前の所有者があちこちに丁寧な書き込みをしていて、学習に使ってくれていたらしいことがわかった。
4年前の九州旅行の際に長崎の市役所の人が2時間もかけて調べてくださった除籍謄本から、養子に行ったこの曾祖父の実家が玉名郡大野村大字野口だったことが、番地にいたるまで判明していた。通常ならそれで終わるところだが、曾祖父の旧姓は大野なのだ。大野村だから大野さんだったのかと、軽い気持ちで調べ始めたところ、『姓氏家系大辞典』に玉名郡大野荘や大野別府に関する長い記述があり、資産家だったのに、一家を離散させた放蕩親父として子孫には伝わっていた虎雄の実父は、調べるに価する興味深い人物であった可能性がでてきたのだ。そこで、玉名の地元史の本を大枚をはたいて購入してみたものの、長いこと本棚に鎮座したままになっていた。
この1週間余り、これらの地元史を読んで知ったことは驚きの連続だった。大野という名が記された最古の記録は、『肥前国風土記』の高来郡の項に、景行天皇が肥後国玉名郡長渚浜の行宮に滞在していたとき、「神大野宿祢」に島原方面を視察させたという記述らしいが、玉名には江田船山古墳をはじめ多数の古墳があり、大野氏の故地と考えられている築地の南から、長さ6m超と5m超の巨大木棺が二基出土しているほか、菊池川の対岸ではあるが、やはり玉名市の斎藤山遺跡からは、日本最古といわれる弥生時代の鉄斧が出土していることを、『歴史玉名』に掲載された講演録から知った。ネット上で読めた論文から、この鉄斧が中国北東部にあった燕国の鋳造品と考えられていることなどもわかり、船山古墳から私が想像したことが的中したようなのだ。この古墳から出土した金銅製飾履には亀甲繋ぎ文が刻まれているが、大野氏一族には幕紋として亀甲を使用していた家や、のちに亀甲氏を名乗った家があり、何らかの関連がありそうだ。なにしろ、『玉名市史』はかつてここに吉野ヶ里のような「大野国」が存在したに違いないと推察しているのだ。「野口という大字名は大野の入口という意味であろう」とも。大野別府と呼ばれていた時代は250町だった領地が、どんどん失われ、大野氏が最後までいた場所の一つが野口らしい。
驚くべきは古代史だけではない。高瀬はおそらく自由港津のような発展を遂げたと考えられており、歴史を通じて近隣諸国の人びとが出入りしてきた場所だった。元寇、日明貿易、ポルトガルの宣教師による布教活動など、地方史とは思えないほど国際色豊かな歴史が繰り広げられたあと、この地も戦国時代に突入し、大野氏は小代氏によって滅亡させられたのだという。悲運の大野氏を慰霊した四十九池神社まであるようだが、大野一族は死に絶えたわけではなく、歴史の舞台からは姿を消した、ということらしい。祖先が滅亡してしまっては、私にはちょっと都合が悪い。
もちろん、私の高祖父に当たる「放蕩親父」が明治になって適当に大野と名乗ることにした可能性は皆無ではないが、これだけの歴史的背景のある大野村で、まるで関係もなくその名字を名乗ることは、通常では考えにくい。コロナ禍でなければ、1週間の調査旅行にでかけたいところだが、こんなときにひょっこり訪ねてくるよそ者が歓迎されることはないと思い、とにかくまずは下調べをすることにした。滅亡の年も、説によって30年の隔たりがあるようなので、小代氏文書などが収載されている『玉名市史 資料編5』をさらに古本で買ってしまった。玉名に行ったこともないのに、これほど市史を読んでいるのは私くらいではないだろうか。
一方、曾祖父の虎雄自身については、拓殖大学の百年史関連の書物からいくらか情報が得られた。名称も教育機関として位置づけもたびたび変わっているので当時何と呼ばれていたか、まだ確かめていないが、のちに拓大となった学校でロシア語が開講されたのは、ロシア革命の年、1917年で、曾祖父がロシア語の講師として雇われたのはその3年後にロシア語が同大の主要3言語に認定された年だった。同僚の多くは学士や博士であるなか、曾祖父の学歴欄は空白になっていたが、「出身地長崎県の長崎露語研究会、後には清国旅順でロシア語を学んだ。桜井[又男]と同じく陸軍通訳を経て、大正4年には参謀本部の嘱託としてロシア語業務を担当した」と『拓殖大学百年史 大正編』に書かれていた。どこでロシア語を学んだのか、ずっと疑問に思っていたが、私が想像したとおり大陸に渡っていたのだ! 娘が昔、叔父から聞いたところでは、曾祖父は1906年4月、まだ21歳のときに勲六等単光旭日章をもらっているので、おそらく旅順にいたころに日露戦争が勃発して現地採用の通訳として雇われ、何らかの功績があったのだろう。第一次世界大戦が大正3年に始まっているので、そのころ再び陸軍で仕事をしたのだろうか。拓大には、似たような経歴の同僚が何人かいるので、正規の大学教育は受けていなかったが、教員として採用してもらえたようだ。拓大関連の論文には「明治45年二松学舎卒業」とも書かれていた。二松学舎は当時まだ大学ではなく、漢学塾だったようだ。
1924年から1943年にかけて書かれた論文が数本確認されたほか、『レーニンの帝国』という訳書が1924年にでているようだが、これは未確認だ。百年史の昭和編には、拓大のロシア語研究会の会長を務め、昼休み時間に作文、翻訳の課外授業を行なったほか、週一回の研究論文発表会の指導にも当たったと書かれていた。1933年7月には満州産業建設学徒研究団の団長に、拓大の永田秀次郎学長が団長として就任し、そのころには教授になっていた曾祖父が研究団員として参加した写真が、100周年記念のアルバム『雄飛』のなかにあった。1938年ごろには学生主事を務めていたこと、1944年に鉱山科新設の申請がだされた際には、専任の教授として70時間の受持時間となっていたことなども、いくつかの論文からわかった。
百年史には「1947年まで、実に27年にわたり本学でロシア語を教えた」と書かれていたが、叔父からは48年6月24日に在職中、肺炎で死亡したと聞いていた。ペニシリンが手に入っていたら助かったと言われ、娘は高校時代にペニシリンについてあれこれ調べたようだ。東京大空襲で西大久保の家が全焼し、長野県の仁礼村に疎開していたが、曾祖父は単身、東京に戻り、学内の一室に寝泊まりしていたという。母の一家が戦後、松代に引っ越したのが1947年秋以降で、引っ越してすぐに虎雄と孫たちだけで象山に登ったそうなので、本当に急死だったのだろう。電話連絡を受けて動転した祖母が、たまたまその場にいた実母に向かって「お母さん」と呼んだことが子供にとって印象深かったことや、病弱な赤ん坊だった末っ子の世話で、葬儀にでられなかった祖母の代わりに、母たち姉妹が3人だけで汽車に乗って上京したこと、葬儀の場で虎雄の弟に会い、そこでコッペパンをたくさんもらったことなどは、私が何度も母から聞かされた話だった。この弟はコッペパンを土産にもってきたばかりに、本名は忘れられ、「コッペパンの叔父さん」としてしか記憶されていない。伯母によると、その後に学葬があったのか、参列した祖母が泣き崩れていたという。
一人っ子だった祖母は父親に甘やかされて育ったのだろう。晩年になるまで子供のころに買ってもらった幅広のリボンを大切にもっていて、まるで形見分けのように、すでにボロボロになったその一部を切って私にくれたことがあった。当時の私に、祖母の話をもっと聞いてあげる気持ちの余裕がなかったことが惜しまれる。
西大久保の家で盆栽を育て、九官鳥を飼っていた虎雄