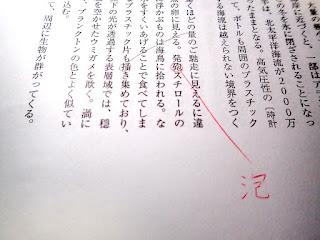小説の出だしはちんぷんかんぷんで、我慢して読み進めると、序幕の後半で怪しげな黒衣が「浅草瓦町の万造」について語り始める。それを受けて娘姿の人形が、「『浅草茅町北、瓦町』」と返す。このように二重鉤括弧で表示された歌舞伎のセリフを挟みながらところどころに挿入される黒衣と人形のやりとりが、劇中の全能の語り手や解説者のような役割であることに気づくまでにしばらく時間がかかった。「『アレ、そんな上手をいまさら』」といった表現や、「くつくつ笑う」、「かつん」、「こつん」といった気になるオノマトペが多用され、時代がかった雰囲気を醸しだす。人力車などと書かずに、俥と表現したり、露天商や的屋などと言わず、香具師(やし)としたり、言葉が巧みだ。
「そう。その借家だ。間口九尺の小さな家だが、低いながらも二階があって、狭いながらも庭がある」と、万造の借家について黒衣が説明をつづける箇所を読みながら、かつて瓦町にあった上田藩の瓦町藩邸、のちの徳川慶勝の屋敷を想像した。瓦町の一部は江戸時代から町屋で、上田藩邸の向かいには文久2(1862)年から佃煮屋の鮒佐があったし、明治2年には内田九一の写真館なども開業している。小説には菊枝という柳橋の芸者上がりの女性も登場する。柳橋の花街は、茅町と呼ばれていた一角から総武線の線路を越えて南に広がり、神田川に突き当るまでの一帯にあった。
表紙画にも描かれている凌雲閣に夜間こっそり登る場面もある。この高層ビルは、「英吉利の技師、バルトンの設計によって明治二十三年に竣工した。煉瓦造りの十階の上に木造の二階があって、その眺望は信じられないほど広大なものだ」という説明のとおりの建物で、浅草寺の西にあったが、関東大震災で半壊し解体されたようだ。作中「麻布汐見坂」とされた鷹司邸は、実際には麻布本村町の、現在はフィンランド大使館がある場所にあった。麻布の潮見坂はもっと北寄りの旧岩崎庭園の近くにある。「上野戦争で廃墟と化したその聖域には、博物館が建ち、植物園が設けられ、勧業博覧会の会場が設置された。文明開化を象徴する広大な公園だが、そこには江戸がたわめられている」などという、考えさせられる一文もある。
舞台は一応、明治29年という時代設定になっているのだが、祐宮、つまり明治天皇がその4月に崩御して新しい時代に入るというパラレルワールドなので、歴史をかじった人には頭が混乱するものがあるだろう。万造は新聞記者の平河新太郎とともに、話の中心的な役割をはたす。平河のほうは会津藩士の子孫という設定だ。
私がもともと関心をもっていた実在の鷹司煕通は、明治天皇の大喪の礼で祭官長を、大正天皇の即位式でも大礼使長官を務め、1918(大正7)年まで生きたが、作中では10年前に50歳で死去していて、その息子たちが鷹司家の家督を巡って悶着を起こすという筋書きになっている。よく見ると鷲司だったり、異体字だったりするのかと虫眼鏡で拡大してみたが、そういうわけでもない。「煕通卿は同じく摂関家の九条家から養子に入った人だ」、「ともあれ、煕通卿はそういう人だったわけだね。進歩的な開国派、尊王攘夷を主張した祖父輔煕とはおりあいが悪かった。当時の公家のほとんどが攘夷を頑強に主張していたから、公家の中でも異端だったと言っていい」といったセリフは、おおむね正しい情報も伝えるので、余計に頭がこんがらがる。
さらに誤解を招くのは、「堀田正睦の勅許工作に密かに協力して、それで輔煕卿の勘気をこうむったらしいね」、「煕通が最初に政治表の近くに姿を現したのは堀田正睦の勅許工作の折、次の井伊直弼のおりにも再び暗躍をおこない、勅許には結びつかなかったものの、港を持つ沿岸の諸藩の説得に成功」などという表現が、何度も繰り返されることだ。「神仏分離だよ。神と仏を分けろという。先代はあれに猛反対なさっていたからね。反対に父[煕通]はその推進派だった。あの人はいつものような西洋を睨んでの理屈でね」という下りなどは、どこから湧いてでたアイデアなのか。私に思い当たるのは唯一、煕通の兄で興福寺塔頭の大乗院の門跡となったものの、神仏分離で還俗した松園尚嘉くらいだ。一連の出来事で興福寺は廃寺寸前にまでなり、大乗院の跡地は奈良ホテルになった。実在の人物名を使って、論議の的となりやすく、かつ無関係の史実との関連をほのめかしながら、すべてフィクションだと言ってしまえば、それで済むのだろうか。
歴史上の鷹司煕通は、堀田正睦が安政5(1858)年に勅許を得るために上京した際に応対した関白、九条尚忠の息子で、そのわずか3年前に生まれている。鷹司輔煕は、文久3(1863)年に1年未満、関白を務めたのち謹慎処分となり、18歳になったばかりの息子の輔政も亡くしたため、九条家から煕通を養嗣子とした。したがって、輔煕は養祖父ではなく、養父に当たる。煕通には小説と同様に息子が4人いたが、長男の信輔は日本鳥学会の第2代会頭を務めた人であり、その息子で交通博物館調査役だった平通は愛人宅で変死を遂げた。小説のなかに登場する鷹司常煕、通称、常(ときわ)のモデルはこの親子なのだろうか。次男は軍人であり、3男、4男は小説の登場人物と同名だが、それぞれサボテンの研究家と水族館の館長だったようだ。煕通の妻も徳大寺家の出で、小説のように陰陽道の倉橋家の人ではない。
「これは父が建てました建物です。[……]西洋の真似ではいけない。外国のお客さまは日本をご覧になりたいのだから、と生前よく申しておりました」)。あるいは、「父は迷信じみたことが本当に嫌いだったのです。占いやまじないも嫌いで」、「封建的なことや前時代的なことも嫌っておりましたし」などという煕通の性格描写は、実際がどうあれ、九条家の出であることを考えれば、あながち間違っていないかもしれない。
瓦町の万造は小説のなかで、こんなことを言う。「世の中には本当のことと噓のことがございます。[……]噓を規制すれば、誰もが本当の顔で嘘をつく。噓が本当としてまかり通ってしまうことと、ふたつが曖昧なことは同じようでまるで違う気がいたしますんです」。その前段には、「河童だの人魚だの、見世物があっても本物だったことはござんせん。それでも人が集まるのは、噓でもいっこうに構やしない、むしろ噓を観るために集まっていたからじゃァありますまいか」。これがフィクションにたいする著者の姿勢だろうか。そこに込められた真理を見抜いた読者が、現実の歴史の謎に目を向けてくれるならよいが、大半の人は空に浮かぶ生首や人魂売り、赤姫姿の闇御前、火炎魔人など、奇をてらった仕掛けに気を取られて、著者のつくりだす虚構の世界に浸って終わるのではないのか。そうなると、部分的に本物で大衆を惑わすフェイクニュースと大差なくなる。
「農民を踏み台にして背伸びして、開化の猿芝居を続けるつもりか」、「まずは列強の搾取を排除しなければならない。関税自主権の回復は急務だ」、「重石を乗せてたわめたものは、重石を跳ねのけようとするもの」、「開化など、嘘だ。だれもが新しい時代がきたふりをしているだけだ。四民が平等ならなぜ華族がいるのだい」。あまりにも急激な変化に順応できない明治の社会を巧みに描いているようだが、瓦町の万造はこんなことも言う。「開国するべきではなかったのです。せっかく呪力で国を包んであったのに、そこに風穴を開けてどうします。開化などしてはならなかった。国を守ってきたものを、迷信だなんだのと切って捨ててどうするのです」
小野不由美は私と同世代の作家で、トールキンとC・S・ルイスのみならず、私が大好きなアーサー・ランサムにも影響を受けているのだそうだ。出身地に怪奇伝説が多く、幼少期から両親にせがんで怪奇話を聞くとウィキペディアにはある。福沢諭吉を輩出した中津はそんな土地柄なのだろうか。『東亰異聞』は1993年に、まだ彼女が30台前半のときに第5回日本ファンタジーノベル大賞の最終候補作になった作品だという。かなりの才能の持ち主だとは思うけれど、私には実際の歴史の謎解きのほうがはるかに面白い。歴史の闇に葬られた謎はいくらでもあるのだから。