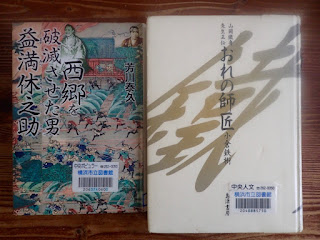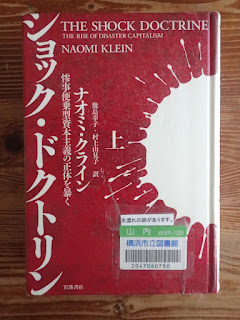ミシオネス州「サン・イグナシオにおける日本人の発展をもたらしたのは山口喜代志である。山口は1910年に旅順丸でブラジルにわたり、1911年にアルゼンチンにやってきた。[……]山口は1925年にサン・イグナシオに入植し、養蚕用の桑を植え、ジェルバの栽培もはじめた。山口喜代志も日本人の入植者に協力を惜しまなかった。1926年ごろからサン・イグナシオに入植したのは以下の人々である」。このあとに13人の名前が列記され、そのうちの1人が「東郷不二夫」となっていた。次のページには1931年のアルゼンチン日本公使館の報告リストがあり、そこには入植年1927年の「東郷不二夫」、本人を含む家族数3、所有面積40ha、マテ樹木数8,000本と掲載されている。
「原典で姓名の誤りとおもわれる部分は修正した」とあるので、不二夫は二夫だった可能性が高い。前述したように、二夫さんは1930年に入籍したが、妻はまだ日本に残っていた。長子は1934年生まれなので、入籍と同時に、同行した義弟の移民申請もだされ、それが公使館の記録となって「3人」世帯と認識されたのだろうか。
サン・イグナシオに最初に入植した山口喜代志は佐賀県出身なので、彼を頼ってのことだったかもしれない。公使館の報告書には、「日本人全員が永住の決意をいだき、異口同音に子孫百年の大計をたてると称して焦らず騒がず着実にその業務に従事していた。そして互いに助け合い、自家製の料理を持参しあっては農業の改善について話し合い、一獲千金を夢みる者はまったくいなかった」と書かれていたという。1931年時点で土地代を完納している人のなかに、二夫さんは含まれていないが、所有面積はかなり広いほうだ。
18世紀末にフンボルトとともにアルゼンチンと探検したエメ・ボンプランが、のちに入植してジェルバ(イェルバ)・マテという低木を栽培し、アルゼンチン現地民の飲料だったマテ茶を一躍有名にしたのは、サン・イグナシオのすぐ近くのサンタ・アナだった。私の娘はこの話を子供用の科学絵本で読んで以来、マテ茶を飲みつづけているのだが、二夫さんがアルゼンチンで生計を立てていたのが、このマテ茶だったようだ! 「マテ茶の原料となるジェルバ・マテは、〈オーロ・ベルデ(緑の金)〉と呼ばれた。[……]そしてこのジェルバ・マテを供給するのが、アルゼンチンの北部、パラグアイ、ブラジルとの国境がいりくむミシオネスである」と、移民史の本には書かれている。トラクターなどない時代、40ヘクタールもの土地を耕して、二夫さんが1人で8000本もの低木を植えたのか、それともその予定だったのか、いずれにせよたいへんな作業だったに違いない。
上下2巻のこの本に、二夫さんに関する情報はほかに見当たらなかったが、1939年5月9日付の『亜爾然丁時報』に掲載された〈サン・イグナシオ通信〉には、この地域の日本人会の名称を「アルトパナラ日本人会」と改称し、任期2年で幹事を5人選んだなかに二夫さんの名前があった。一緒に幹事を務めた土居祐緑、寺本芳雄の2氏の名前は1931年のリストにもあり、入植当初からの仲間だったようだ。1942年3月7日付の同紙には、「故三浦哲蔵氏葬儀及墓碑建造費寄付者芳名」のなかに、「拾五弗宛[ずつ]」を寄付したとして二夫さんの名前があった。移民して十数年が経ち、少し経済的に余裕がでてきたのだろうか。
戦前編には、初期の移民やその背景が書かれている。日本からの定着移民第1号は、1886年に入国したと言われる三浦の三崎出身の牧野金蔵だが、1989年に日本とアルゼンチンが正式に外交関係を結んだ2年後に最初に移民した2人のうち1人は佐賀県東択浦郡湊村(現在の唐津市湊)出身の16歳の若者、榛葉贇雄、もう1人は鳥海忠次郎という13歳の少年だった! 榛葉は少なくともかなり成功して、スペイン語の著作も数点残したようだ。その後、1904年に東京外語大出身の丸井三次郎と古川大斧が農商務省の海外実業練習生としてアルゼンチンに渡った。二夫さんがアルゼンチンを選んだ理由には、こうしたいくつかの前例があったからに違いない。1918年ごろのリストを見る限り、佐賀出身者はときおり見られる程度で、多くは沖縄、鹿児島、熊本、福島などからきていた。
二夫さんが移民を決意した理由が何だったかはわからないが、この時代に佐賀から東京の大学に進学していたとすれば、経済的に困窮した末ではなかっただろう。兄の嘉八は佐賀師範学校出なので、次男にはるかに教育費をかけたことになる。ただし、彼らの父親は炭鉱に手をだして痛い目に遭った挙句に、32歳(数えで34)で他界しているので、妹を含めた3人の子供たちは母親によって育てられている。アルゼンチンから私のもとに届いたメールには、この曾祖父母の名前が記されていて驚いたが、考えてみればそれが二夫さんの戸籍にあった唯一の日本の記録なのだろう。ちなみに曾祖父はなぜか戸籍では徳市なのに、墓標には徳一と記されている。曾祖母はスエというが、Sueを手書きした文字が判読しづらかったのかメールにはJueと書かれていた。前の記事に掲載した家族写真の前列のおばあさんがスエさんと思われる。
それにしても、南米大陸の大西洋側の南端にあるアルゼンチンは、日本からはおよそ行きづらい国だ。移民の多くはブラジルやペルーなどにいったん渡ったあと、アルゼンチンへ移動したという。インド洋周りで行く人もいたようだが、太平洋航路で移住した人びとは、1910年にアンデス山脈を抜ける鉄道トンネルが開通すると、チリのバルパライソから列車でアルゼンチンに入国したそうだ。ただし、冬季に積雪で汽車が突如、不通になり、雪のなかを徒歩でアンデス越えした人びともいた。
戦後編にもいろいろ興味深いことが書かれていた。戦後の日本人の海外移住は1947 年にアルゼンチンから始まったという。「戦後の日本人花嫁たち」という節には、「定住後に彼らが伴侶として求めたのが日本の女性だった。なんといっても価値観と生活勘を共有できる生活環境が整ったとき、多くの日本人男性は日本にいる親や親戚や知人に伴侶探しを依頼した。中には新聞広告で花嫁を募集した者もいた」と書かれていた。「いわゆる〈写真花嫁〉とか〈移住花嫁〉と呼ばれる女性の移住は、日本人移住者の間だけで行われたものではなく、アルゼンチンに大量移住したイタリア人をはじめ、スペイン人やポルトガル人などの社会でも実行されていた」ともある。
「二世たちの歩み」という節には、私や弟がにわかにアルゼンチンの親戚探しを始めるきっかけとなった軍政時代のことも書かれていた。「軍事政権の前後に3万人の行方不明者が記録されていた。そのうち15名は日系人だった」。「ほとんどが戦前移住者の子供」だったという。こうした時代を親戚たちがどうくぐり抜けたのか、いつか話を聞けたらと思う。
『アルゼンチン日本人移民史』戦前編と戦後編(社団法人 在亜日系団体連合会、アルゼンチン日本人移民史編纂委員会刊、2002、2006年)
ミシオネス州のジェルバ・マテの大農園(画像は、WikipediaのYerba mateの項より拝借)『亜爾然丁時報』1939年5月9日付(国際日本文化研究センターのサイトより拝借)